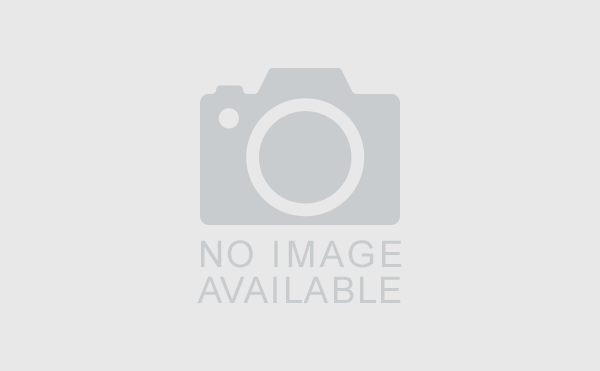痩せるための科学的根拠を持った方法
体重を減らすためには、「消費カロリー > 摂取カロリー」というエネルギー収支の原則が基本となります。これは、数あるダイエット法の根幹をなすものであり、いかなる方法をとるにせよ、この原則を外れることはありません。
1日の消費カロリーを知る
まずは、自分の1日における**消費カロリー(TDEE: Total Daily Energy Expenditure)**を把握しましょう。これは、Harris-Benedictの式などを使って、年齢・性別・身長・体重・活動量に基づいて計算することが可能です。
下記のリンク先では、簡単に計算できますのでぜひご活用ください。
摂取カロリーの設定:目標は「無理なく続けられる赤字」
「少なければ少ないほど痩せる」と思いがちですが、過度なカロリー制限は筋肉の減少や体調不良、リバウンドの原因になります。したがって、現実的かつ持続可能なカロリー設定が大切です。
私たちが推奨する摂取カロリーの目安は、
「1日の消費カロリーから500kcalを差し引いた量」です。
この赤字(カロリー不足)を毎日積み重ねることで、以下のようなペースで脂肪を減らしていくことができます:
- 脂肪1kg ≒ 約7,000kcal
- 500kcalの赤字 × 14日 ≒ 1kg減(約2週間で脂肪1kg減少)
無理なく、かつ科学的に体脂肪を落とすための最も基本的な指針といえます。
食事内容:タンパク質中心の食事を意識する
カロリーだけでなく、「何を食べるか」も非常に重要です。特に、ダイエット中は「タンパク質(Protein)」を意識的に摂取してください。
タンパク質の目安量
- 1日あたり、体重1kgあたり1.5〜2.0gのタンパク質を目指しましょう。
- 例:体重70kgの方 → 105〜140g/日
- 1食あたり30〜50g程度を意識して取りましょう。
※肝疾患・腎疾患のある方は、主治医にご相談ください。
“Protein”という言葉はギリシャ語の「proteios(第一の・最も重要な)」に由来しており、栄養学における重要性を象徴しています。タンパク質は筋肉や皮膚、内臓などの構成要素であり、ダイエット中に損なわれがちな筋肉の修復・維持にも不可欠です。
栄養バランスの基本:脂質と炭水化物について
脂質は“悪”ではありません
ダイエットにおいて「脂質=太る原因」「カットすべき悪者」といった誤解が根強くあります。しかし、脂質は生命維持に不可欠な栄養素です。
- 脂質はコレステロールの材料であり、
- そのコレステロールから「ホルモン(テストステロン・エストロゲンなど)」が合成されます。
これらのホルモンは、性機能だけでなく、代謝・筋肉の維持・精神状態・活力にも関わる重要な要素です。
特に男性においては、テストステロン値が低いと基礎代謝が落ち、筋肉がつきにくく、体脂肪が増えやすくなる傾向があります。
過度に脂質を制限すると、肌荒れ、疲労感、ホルモンバランスの乱れなどを引き起こします。
そのため、ダイエット中であっても、1日あたり50g程度の良質な脂質はしっかり摂るようにしてください。一般的には体重1kgあたり1.0g未満の脂質は下回らないようにしましょう。
(例:体重60kg→脂質は60g/日前後)。
おすすめの脂質源:
- オリーブオイル、えごま油、アマニ油などの植物性油
- アーモンド、くるみなどのナッツ類
- 青魚(サバ、イワシなど)のEPA・DHA
女性にとって特に重要なのが、「エストロゲン(卵胞ホルモン)」の存在です。
エストロゲンは、以下のような多面的な作用を持っています:
- 月経周期の調整
- 骨密度の維持(骨粗鬆症予防)
- 皮膚・髪の健康維持
- 自律神経の安定・気分の調整
- 内臓脂肪の抑制作用
- インスリン感受性の維持による代謝サポート
このように、エストロゲンは女性の健康、そして代謝機能そのものに大きく関与しています。
過度な脂質制限を行うと、エストロゲンの産生が低下し、月経不順や無月経、骨量低下、肌荒れ、気分の変調など、さまざまな健康被害が生じる可能性があります。特に若年女性や低体脂肪率の女性では注意が必要です。
補足:月経とダイエットの関係
女性の場合、体脂肪率が極端に低下すると月経が止まることがあります(機能性視床下部性無月経)。これは、エネルギー不足やホルモン異常により、生殖機能よりも生存を優先する身体の自然な防御反応です。
月経が止まるほどのダイエットは、「痩せている」状態ではなく、「ホルモンのバランスが崩れている病的な状態」です。
美しく健康的に痩せるためには、適切な脂質摂取とホルモンバランスの維持が不可欠です。
このように、脂質の摂取はダイエットを妨げるものではなく、女性においてはむしろホルモンバランスを保ち、健康的な代謝を支える土台となる重要な栄養素です。極端なカットは避け、良質な脂質を意識的に摂取しましょう。
炭水化物は量が鍵
炭水化物(糖質)は、エネルギー源として非常に重要な栄養素ですが、過剰摂取は体脂肪の増加に直結します。特に、血糖値を急上昇させる単純糖質(白米、パン、麺類、砂糖など)は、インスリン分泌を促進し、体脂肪の蓄積を加速させます。
そこでおすすめするのは、以下のような方法です:
- 炭水化物は控えすぎず、適量を守る
- 主食は玄米・全粒粉パン・オートミールなど低GI食品に置き換える
- タンパク質と脂質で摂取カロリーをまず構成し、不足分を炭水化物で補うという順番を意識する
このように、カロリーだけでなく栄養素の内訳=PFCバランス(Protein・Fat・Carbohydrate)を考えることが、健康的な減量の鍵です。
「食べてはいけないもの」ではなく「避けるべき組み合わせ」
ダイエットで最も避けたいのは、脂質+炭水化物の組み合わせです。この組み合わせは、強烈な食欲刺激をもたらし、ついつい“やめられない・止まらない”状態を生み出します。
典型的な例:
- フライドポテト
- 揚げ菓子(ポテトチップス、かっぱえびせん等)
- ドーナツ、クリームパン、ピザ、ラーメンなどの高脂質・高糖質食品
これらは「美味しさ」を感じやすい構成であり、脳の報酬系を刺激して過食を誘発することが神経科学的にも分かっています。
こうした高脂質・高糖質の超加工食品(Ultra-Processed Foods)は、意識して避けるようにしましょう。
アルコール:減量中はどう向き合うべきか?
アルコールもまた、ダイエットの障害となりうる要素です。以下の理由から、減量中は可能な限り控えることをおすすめします。
- アルコールは食欲を増進させる
- 代謝の優先順位が変わり、脂肪燃焼が後回しになる
- 飲酒により判断力が鈍り、過食を招きやすい
とはいえ、「完全にやめるのは難しい」という方も多いでしょう。そのような場合は、以下のような工夫を取り入れてください。
減量中でもOKなアルコールの摂り方
| 種類 | 特徴・アドバイス |
|---|---|
| 焼酎・ウイスキー・ジン | 糖質ゼロ。炭酸水やお茶で割って飲むと◎ |
| 赤ワイン(適量) | ポリフェノールが含まれ、健康効果も一部あり |
| ハイボール | ビールよりカロリー・糖質が少なくおすすめ |
| 避けたいもの | ビール、日本酒、梅酒、カクテル類などの甘いお酒 |
また、飲酒の前後には高タンパク・低脂質の食事を意識すると、血糖値の急上昇や脂肪蓄積のリスクをある程度抑えることができます。
Intermittent Fasting(間欠的断食)の重要性
断食(Fasting)は、摂取カロリーを無理なく抑えるための非常に有効なテクニックの一つです。近年では、1日〜2日まったく食事を摂らない長時間断食や、酵素ドリンク・ハーブティーなどを摂取しながら行うファスティング(semi-fasting)も注目されています。
これらの方法は一部で有効性が示されていますが、我々が推奨するのは、より日常に取り入れやすい「Intermittent Fasting(間欠的断食)」です。
食事時間を制限する=自然に摂取カロリーが減る
たとえば、1日1食しか食べない生活を想像してみてください。果たしてその1食で、3食分のカロリーを摂ることはできるでしょうか?
多くの場合、それは不可能です。胃袋には限界があるのです。食事のタイミングを意図的に制限することで、“無意識のうちに”摂取カロリーを減らすことが可能になります。
まずは12時間断食からスタート
Intermittent Fastingの第一歩は、**「12時間の断食」**です。睡眠時間を含めることで、誰でも無理なく始められます。
- 例:夜20時までに夕食を終え、翌朝8時以降に初めて食事を摂る
慣れてきたら、次のステップへ:
| ステップ | Fasting時間 | 食事可能時間の例 |
|---|---|---|
| 初期 | 12時間 | 20時〜翌8時 |
| 中期 | 14時間 | 20時〜翌10時 |
| 上級 | 16時間以上 | 20時〜翌12時 |
最初は空腹感を覚えるかもしれませんが、体が慣れると空腹時間も心地よく感じられるようになります。
断食中であっても、食べられる時間帯には、十分なタンパク質・脂質・炭水化物をバランスよく摂取し、過度な制限にならないように注意しましょう。
運動:筋力トレーニングと有酸素運動の両輪を
ダイエットにおいて、運動は欠かせません。特に重要なのは、以下の2つの運動です。
筋力トレーニング(ウェイトトレーニング)
体重を減らす過程では、脂肪だけでなく筋肉も同時に減少していきます。これを防ぎ、筋肉を維持・増強するには、週2〜3回の筋力トレーニングが有効です。可能であればジムに通い、段階的に重さを増やしていく形でウェイトトレーニングを行ってください。
筋肉量が増えると、基礎代謝(BMR)が向上します。実は、1日の総消費カロリー(TDEE)の約60〜70%は、この基礎代謝によって消費されており、運動自体のカロリー消費は全体のわずか5%程度です。
したがって、「消費カロリーを上げるためには、基礎代謝=筋肉量を増やすこと」が最も効率的です。
有酸素運動(Aerobic exercise)
もう一つの柱が、有酸素運動です。ランニングや水泳、バイクなどさまざまな方法がありますが、私たちは「Walking(ウォーキング)」を推奨します。
- 時間・場所を選ばず、誰でも・どこでもできる
- 継続しやすく、習慣化しやすい
- 関節への負担が少ない
特別な運動というより、生活の中に溶け込ませて実践することが重要です。1日あたり15,000歩を目標にしてみてください。
下記に、**「1日15,000歩を達成するための15のコツ」**をまとめたPDF資料をご用意しました。ぜひご活用ください。
※1日15,000歩のためのテクニック集
空腹時に有酸素運動を取り入れると脂肪燃焼効率がアップ
空腹時には、血中のインスリン値が低下しており、脂肪分解(リポリシス)が促進されやすい状態です。このタイミングでwalkingなどの有酸素運動を取り入れると、脂肪がより効率的にエネルギーとして使われます。
今日からできる!4週間のアクションプラン
| 週 | 筋トレ(全身) | 歩数目標 | 摂取カロリー | Fasting時間 |
|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 週2回 | 1日8,000歩以上 | 消費カロリー −500kcal | 12時間(20〜8時) |
| 第2週 | 週2回 | 1日10,000歩以上 | 消費カロリー −500kcal | 14時間(20〜10時) |
| 第3週 | 週3回 | 1日12,000歩以上 | 消費カロリー −500kcal | 14時間 |
| 第4週 | 週3回 | 1日15,000歩以上 | 消費カロリー −500kcal | 16時間以上(可能なら) |
まとめ
- まずは自分の1日の消費カロリーを把握しましょう。
- 摂取カロリーは「消費カロリー−500kcal」が目安です。
- タンパク質中心の食事で、筋肉量を保ちましょう。
- 炭水化物は質と量を調整し、不足分を補う形で摂取するのが理想です。
- 脂質は制限しすぎず、ホルモンバランスを保つために1日50g程度は摂取を。
- 高脂質・高糖質の「やみつき食品は意識して避ける」ことがポイントです。
- さらに、「Intermittent Fasting(断続的断食)」も有効です。
無理な食事制限や極端な運動は必要ありません。続けられる工夫をこそ、医療的にサポートいたします。